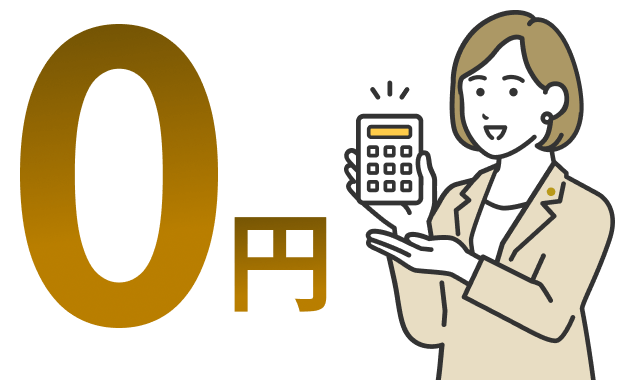配偶者の遺留分の割合は? 具体的な計算方法や請求方法について
- 遺留分侵害額請求
- 遺留分
- 配偶者

亡くなった方の配偶者には、相続できる遺産の最低保障額である「遺留分」が認められています。遺言書によって指定された相続分がゼロであったり、非常に少なかったりしたとしても、適切に対応すれば遺留分を確保することができます。
ご自身の遺留分が侵害されたと思われる場合は、早めに、弁護士に相談しましょう。
本コラムでは、「配偶者の遺留分」について、計算のルールや具体例、遺留分侵害額請求を行う際の注意点などをベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士が解説します。
1、遺留分権利者は誰か? 民法のルールを解説
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です(民法1042条)。
被相続人の配偶者と子は常に相続人となるため(民法890条、887条1項)、被相続人の死亡時点で存命していれば、被相続人の配偶者と子に遺留分が認められます。
被相続人の死亡時点で子が死亡しており、さらにその子(被相続人の孫)がいれば、孫が相続人となります(代襲相続、民法887条2項)。
また、相続人となることに伴い、孫には遺留分が認められます(民法1042条2項)。
ひ孫についても、同様の要領で遺留分が認められることがあります(再代襲相続、同条3項)。
そして、子といった直系卑属がいない場合には、被相続人の直系尊属(両親や祖父母)に相続権が認められます(民法889条1項1号)。
この場合、被相続人の直系尊属に遺留分が認められます。
直系卑属・直系尊属がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
しかし、兄弟姉妹には遺留分が認められません。
被相続人の兄弟姉妹がすでに死亡しており、その子である被相続人のおい・めいが代襲相続する場合も、同様に、遺留分は認められないのです。
なお、本来であれば遺留分を有する者であっても、相続欠格(民法891条)や相続廃除(民法892条)、相続放棄(民法938条)により相続権を失った者については、遺留分は認められません。ただし、相続欠格、廃除の場合には、代襲相続が開始され、これらの者の直系卑属に遺留分が認められます(民法1042条、887条2項、同条3項)。
2、遺留分割合の決定ルール・計算例
各相続人の遺留分割合は、被相続人との続柄に応じて決まります。
以下では、遺留分の割合の決定に関する民法のルールや、相続人構成別の遺留分割合について解説します。
-
(1)遺留分割合の決定ルール
遺留分割合は、以下のルールに従って決まります(民法1042条1項)。
- ① 直系尊属のみが相続人である場合
法定相続分の3分の1 - ② ①以外の場合
法定相続分の2分の1
- ① 直系尊属のみが相続人である場合
-
(2)配偶者がいる場合の遺留分割合
被相続人に配偶者がいる場合、総体的な遺留分割合は「法定相続分の2分の1」です(民法1042条1項2号)。配偶者のほかに遺留分権利者がいる場合、各自の法定相続分を乗じた割合で、各遺留分権利者に遺留分が認められます(民法1042条2項)。
<配偶者がいる場合の遺留分割合の例>
① 配偶者のみが相続人の場合- 配偶者:2分の1(法定相続分は1(100%))
② 配偶者と子2人が相続人の場合- 配偶者:4分の1(法定相続分は2分の1)
- 子:8分の1ずつ(法定相続分は4分の1ずつ)
③ 配偶者と両親が相続人の場合- 配偶者:3分の1(法定相続分は3分の2)
- 両親:12分の1ずつ(法定相続分は6分の1ずつ)
-
(3)配偶者がいない場合の遺留分割合
直系尊属が相続人の場合は「法定相続分の3分の1」、直系卑属が相続人の場合は「法定相続分の2分の1」が総体的な遺留分割合となります。(民法1042条1項)。遺留分権利者が複数人いる場合には、各自の法定相続分を乗じた割合で、各遺留分権利者に遺留分が認められます(民法1042条2項)。
<配偶者がいない場合の遺留分割合の例>
① 子1人のみが相続人の場合- 子:2分の1(法定相続分は1(100%))
② 両親のみが相続人の場合- 両親:6分の1ずつ(法定相続分は2分の1ずつ)
③ 兄弟姉妹のみが相続人の場合
遺留分は認められません
3、遺留分を侵害された場合は「遺留分侵害額請求」
遺留分を侵害された相続人は、遺産を多く取得した他の相続人等に対して、「遺留分侵害額請求」を行うことができます(民法1046条1項)。
-
(1)遺留分侵害額請求とは
遺留分に足りない遺産しか取得できなかった相続人は、不足額の補塡(ほてん)を受けるために、遺留分侵害額を請求することができます。
遺留分侵害額請求を行うと、遺留分額と実際の取得額の差額について、遺産を多く取得した者から金銭の支払いを受けることができるのです。 -
(2)遺留分侵害額・請求額の計算例
遺留分侵害額は、以下の式によって求めます。
遺留分侵害額=遺留分額-実際取得した遺留分の基礎財産額
(遺留分額=遺留分の基礎財産総額×遺留分割合)<遺留分の基礎財産>
以下の財産の総額- ① 以下の期間中に行われた生前贈与
- ② 以下の期間中に行われた生前贈与
相続開始前10年間(婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与に限る)
(b)相続人以外の者に対する贈与の場合
相続開始前1年間
※被相続人に債務がある場合、その全額を控除する。
以下では、具体的な設例に基づき、計算してみましょう。
<設例>- 相続人は配偶者A、子B、子Cの3名
- 相続財産が3000万円
- 公正証書遺言によって指定された相続分は、Aが200万円、Bが2100万円、Cが700万円
- Bに対する生前贈与が200万円(相続発生の6年前)
設例では、配偶者Aは200万円しか遺産を取得できていません。
しかし、配偶者Aには800万円の遺留分が認められます。Aの遺留分額
=(3000万円+200万円)×4分の1
=800万円
したがって、Aの遺留分侵害額は、600万円(=800万円-200万円)です。
また、遺留分侵害額は、遺留分を侵害する遺贈または贈与を受けた者が負担することになります。
受遺者(遺贈を受けた者)がいる場合は、まず受遺者が遺留分侵害額を負担します(民法第1047条第1項1号)。
設例では、受遺者はBとCです。
受遺者が複数である場合は、遺贈の金額に応じて遺留分侵害額を負担するため(民法1047条1項2号)、Bの負担額は450万円、Cの負担額は150万円となります。 -
(3)遺留分侵害額請求権の消滅時効
遺留分侵害額請求権は、「相続の開始および遺留分を侵害する遺贈、または贈与を知った時」から1年で時効消滅します(民法1048条)。
したがって、遺留分侵害額請求を予定している場合には、早めに請求の準備を整えなければなりません。
消滅時効の完成が迫っている場合は、速やかに弁護士に相談したうえで、適切な対応を行いましょう。
4、遺留分など、相続に関するトラブルは弁護士にご相談を
遺留分問題を含めて、相続に関するトラブルが発生すると、相続人間の感情的な対立が起こってしまい、冷静な話し合いができない場合もあります。
そのため、相続トラブルを当事者だけで解決することは困難なことが多いのです。
遺産相続に関するトラブルの調整や解決は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、ご家庭のご状況や相談者の希望を丁寧にヒアリングしたうえで、適切な解決策を提案することが可能です。
遺産分割協議や法的手続きへの対応についても、弁護士に任せることができます。
相続についてのお悩みをお抱えの方は、ぜひ、お早めに弁護士までご相談ください。
5、まとめ
被相続人の配偶者には、遺留分が認められています。
被相続人の配偶者であるにも関わらず、遺言書や生前贈与の内容が偏っていたために遺産をほとんど取得できなかった方は、遺産を多く取得した者に対して遺留分侵害額請求を行うことを検討しましょう。
遺留分問題を含めて、相続トラブルの解決は、当事者間だけでは困難な場合が多々あります。
ベリーベスト法律事務所では、遺産相続に関する法律相談を受け付けております。
遺留分侵害額請求をご検討中の方や、その他の相続トラブルにお悩みの方は、適切な解決を図るため、お早めにベリーベスト法律事務所にお早めにベリーベスト法律事務所にご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|