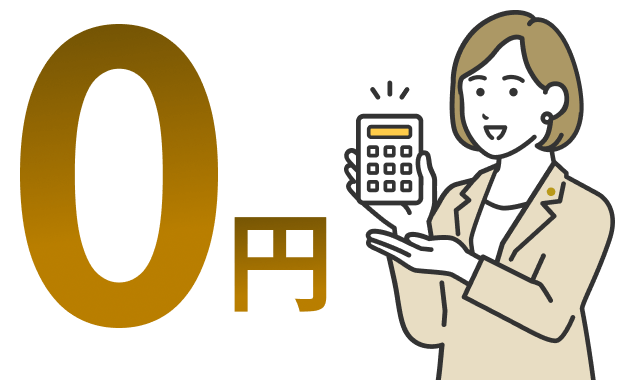相続放棄すれば損害賠償の支払いは免れる? 相続放棄の注意点とは
- 相続放棄・限定承認
- 損害賠償
- 相続放棄
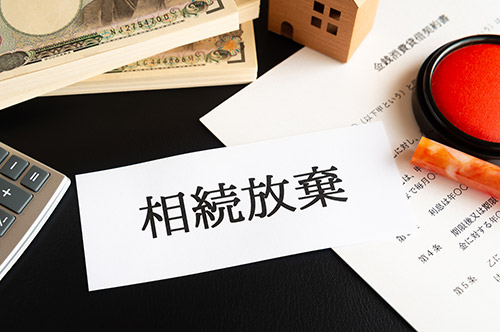
静岡県沼津市のデータによると、2022年9月末時点における沼津市内の人口は19万96人でした。前月末時点と比較すると、139人の減少となっています。引っ越しなどの理由で市を去られた方のほか、お亡くなりなられた方も含まれているでしょう。
亡くなった被相続人が、交通事故や契約違反などが原因で多額の損害賠償債務を負っていた場合、相続放棄をすれば債務の相続を回避することができます。ただし、相続放棄という手続きには、さまざまな注意点が存在します。
相続放棄を検討するなら、早い段階で弁護士に相談しましょう。本コラムでは、損害賠償債務と相続放棄の関係性や、相続放棄をする際の注意点や手続きなどについて、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士が解説します。
1、損害賠償債務と相続放棄の関係性
損害賠償債務とは、自らの行為によって他人に生じた損害を賠償しなければならない義務のことを指します。
具体的には、契約違反や不法行為をしてしまった方は、損害を生じさせた相手に対して損害賠償債務を負うことになるのです。
ある方が損害賠償債務を負った状態で亡くなった場合、財産と共に「損害を賠償する義務」も、相続の対象になります。
したがって、原則として、相続人が賠償金を支払う義務を負います。
しかし、相続放棄をすることで、債務を免責することができるのです。
-
(1)相続放棄とは
相続放棄とは、「亡くなった被相続人の資産と負債を一切相続しない」という法律上の制度です。
相続放棄をすると、初めから相続人にならなかったものとみなされます(民法第939条)。
その結果として相続権を失い、資産と負債を相続しないことになります。
相続放棄の主なメリットは、負債を相続せずに済むという点です。
そのため、亡くなった被相続人が多額の債務を負っていた場合には、相続放棄をすることが有力な選択肢となるでしょう。
他にも、家族との関係性が悪くて遺産分割協議に参加したくない方が、相続放棄を検討するという場合があります。 -
(2)相続放棄により、損害賠償債務は免責される
相続放棄をすると、被相続人が生前負っていた債務は、一切相続せずに済みます。
被相続人の損害賠償債務も例外ではなく、相続放棄をすれば支払う必要はありません。
被相続人に対して損害賠償請求権を有していた人は、相続放棄をしていない相続人がいれば、その人に対して支払いを請求できます。
これに対して、相続人全員が相続放棄をした場合には、相続財産管理人による弁済請求申出の公告期間を経た後、相続財産から弁済を受けることになるのです(民法第957条第2項、第929条)。
2、相続放棄をする際の注意点
損害賠償債務の支払いを避けるために相続放棄をする場合には、注意すべき点が複数存在します。
相続放棄を検討する場合には、相続財産の状況をふまえながら、手続き前後の行動にも十分な注意を払ったうえで、手続きを進める必要があるのです。
-
(1)財産も相続できなくなる
相続放棄をした人は、一切の相続権を失います。
つまり、被相続人の債務(負債)を相続しなくてよくなる反面、財産(資産)を相続することもできなくなってしまうのです。
たとえば、実家の土地や建物、高価な時計や宝飾品といった形見など、手元に残しておきたい遺産がある場合にも、相続放棄をすると一切相続できなくなってしまいます。
どうしても失いたくない遺産がある場合には、相続放棄をせずに債務を弁済する、という選択肢も検討すべきでしょう。 -
(2)相続放棄には期限がある
相続放棄には期限があり、いつでもできるわけではありません。
原則として、自己のために相続が開始したことを知ってから3カ月以内に、相続放棄の手続きを行う必要があります(民法第915条第1項)。
この3カ月を「熟慮期間」といいます。
熟慮期間が経過した場合、原則として相続放棄が認められません。
つまり、原則として、被相続人が損害賠償債務を負っていた場合、全額を相続することになってしまうのです。
遺産相続の際には、債務を含んだ相続財産についてできる限り調査を尽くしたうえで、期限内に相続放棄の手続きを完了できるように努めましょう。
なお、熟慮期間を経過した場合でも、家庭裁判所の判断で例外的に相続放棄が認められることがあります。
特に被相続人の債務の存在が後から判明した場合には、判明時点から3カ月以内に手続きをすれば、相続放棄が認められる可能性が高くなります。
ただし、熟慮期間経過後の相続放棄は、家庭裁判所による審査が行われるため、手続きが複雑になってしまいます。
家庭裁判所に対して理由を説明する必要もあるため、常に相続放棄が認められるとも限らない点に注意してください。 -
(3)相続人自身の債務は免責されない|保証・監督義務者・共同不法行為
相続放棄によって免責されるのは、亡くなった被相続人が負っていた債務だけです。
これに対して、相続人自身が負うべき債務については、相続放棄によって免責されることはありません。
被相続人の損害賠償債務に関連する、相続放棄では免責されない相続人の債務(責任)としては、以下の三種類が存在します。① 保証債務
相続人が契約に基づき、被相続人の損害賠償債務等を連帯保証している場合、保証債務は存続します。
保証債務を履行しなければならないのは、損害賠償債務を承継した相続人が債務不履行を起こした場合や、相続人全員が相続放棄をして損害賠償債務が承継されなくなった場合などです。
② 責任無能力者の監督義務者等の責任
被相続人が他人に損害を与えた当時に責任能力を有していなかった場合、監督義務者またはそれに代わって被相続人を監督する者が、被害者に対する損害賠償責任を負います(民法第714条)。
責任無能力者に当たるのは、年少の未成年者(10~12歳未満程度)と、認知症などの精神上の障害により、自己の行為の責任を弁識する能力を欠いた者です(民法第712条、第713条)。
③ 共同不法行為者の責任
被相続人と共同して他人に損害を与えた相続人は、被相続人と連帯して、被害者に生じた損害を賠償する責任を負います(民法第719条第1項)。
相続人全員の相続放棄などにより、被相続人の損害賠償債務が支払われなくなった場合は、共同不法行為者の相続人が損害全額を賠償しなければなりません。 -
(4)法定単純承認に要注意|相続財産の処分・形見分けなど
以下の枠内のいずれかの行為をした相続人、には「法定単純承認」が成立して、相続放棄が認められなくなります(民法第921条)。
- 相続財産の全部または一部の処分(保存行為と短期賃貸借を除く)
- 相続財産の全部または一部の隠匿、私的な消費、悪意による相続財産目録への不記載(高順位相続人が相続を承認した場合を除く)
相続放棄をする際には、その前後の行動にも気を配る必要があるのです。
3、相続放棄をする際の手続き・必要書類
相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出して行います。
申述書を提出する際には、申述者と被相続人の続柄に応じて、以下の書類も添付しなければなりません。
| 被相続人との続柄 | 必要書類 |
|---|---|
| 配偶者 子 |
|
| 代襲相続人である直系卑属(孫、ひ孫……) |
|
| 直系尊属(父母、祖父母……) |
|
| 兄弟姉妹 |
|
| 甥(おい)・姪(めい) |
|
申述書と添付書類を家庭裁判所に提出すれば、後日、照会書面が送られてきます。
熟慮期間と法定単純承認に注意しながら回答を記載して、家庭裁判所へ返送しましょう。
その後、相続放棄が受理されたら、家庭裁判所から証明書を受け取ることができます。
4、遺産相続に関する問題を弁護士に相談するメリット
遺産相続に関するトラブルや疑問点は、弁護士にご相談ください。
弁護士は、相続手続き全般を一括して代行することができます。
相続人同士でもめてしまった場合にも、弁護士であれば間に入って調整を行うことができるのです。
相続放棄の他にも、遺言・遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄など遺産相続の手続きにはそれぞれに法律的な注意点があるため、弁護士のアドバイスを受けることで、手続きを安心して進行することができます。
5、まとめ
相続放棄をすれば、被相続人が加害者として負う損害賠償債務の相続を回避できます。
ただし、相続放棄には期間制限があることや、法定単純承認が成立すると相続放棄が認められないことなどに注意する必要があります。
ベリーベスト法律事務所は、相続放棄を含めて、遺産相続全般に関するご相談を受け付けております。
相続放棄を検討されている方や、遺産相続の手続きに不安がある方は、まずはベリーベスト法律事務所までご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています