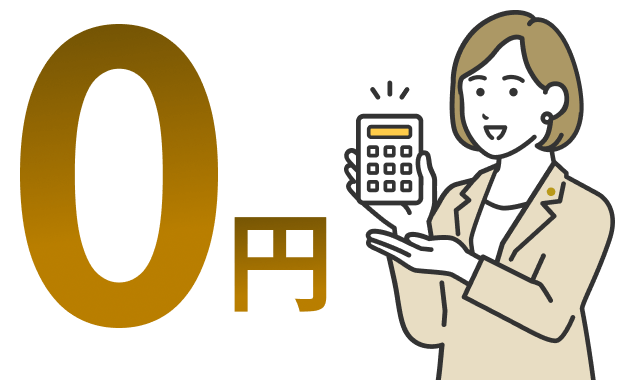相続放棄をするとどうなる?|相続人全員が放棄する場合の注意点
- 相続放棄・限定承認
- 相続放棄
- どうなる

遺産相続に関して、亡くなられた方(被相続人)に多額の借金がある場合や相続そのものに関わりたくない場合などには、「相続放棄」を検討しましょう。
相続放棄は、相続人全員が行うこともできます。ただしその場合は、相続財産清算人の選任申し立てが必要になる点などに注意しましょう。
本コラムでは相続放棄について、メリットとデメリット、相続人全員が相続放棄した場合の取り扱いなどについて、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士が解説します。
1、相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった被相続人の相続財産(遺産)を一切相続しないという意思を表示することです。
相続放棄をした人は、初めから相続人にならなかったものとみなされます(民法第939条)。
-
(1)相続放棄のメリット
相続放棄のメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
① 被相続人の債務を相続せずに済む
被相続人が多額の借金を負っていた場合等には、相続放棄をすれば借金等の債務を相続せずに済みます。
② 遺産分割に関わる必要がなくなる
「遺産分割トラブルに巻き込まれたくない」「疎遠な他の相続人と話すのも億劫だ」という場合には、相続放棄をすれば遺産分割に関わる必要がなくなります。 -
(2)相続放棄のデメリット
相続放棄には以下のようなデメリットがある点に注意してください。
① 遺産を一切相続できなくなる
相続放棄をすると、被相続人の遺産を一切相続できません。形見分けも、被相続人のスーツ、コート、靴など一定の財産的価値のある財産については認められなくなります。
② 相続権が移動し、他の相続人に迷惑がかかるおそれがある
後述するように、相続放棄に伴って相続権が移動する場合があります。
この場合、相続権を取得した者が債権者から請求を受けたり、疎遠な者同士が相続人となって遺産分割トラブルのリスクが高まったりするなど、他の相続人に迷惑をかけるおそれがあることに注意してください。
③ 死亡保険金・死亡退職金の非課税枠が適用されなくなる
相続放棄をした者が取得した死亡保険金・死亡退職金については、相続税の非課税枠が適用されません。 -
(3)相続放棄の手続き
相続放棄をする場合は、家庭裁判所に申述書と添付書類(戸籍謄本など)を提出しましょう。
相続放棄の期限は原則として、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内です(民法第915条第1項)。
期限を過ぎても遅れた事情によっては相続放棄が認められることがありますが、家庭裁判所に対して理由を説明しなければいけません。
相続放棄を検討している方は、期限に間に合うように手続きを行うため、お早めに弁護士までご相談ください。
2、相続放棄をすると、相続人は誰になる?
相続人の一部が相続放棄をした場合、民法に基づく相続順位に従って相続権が移動します。ただし、相続放棄をしても代襲相続は発生しないことに注意しましょう。
-
(1)民法に基づく相続順位に従い、相続権が移動する
民法の規定により、被相続人の配偶者が常に相続人となるほか(民法第890条)、以下の相続順位に従った最上位者が相続権を取得します(民法第887条第1項、第889条第1項)。
- 第1順位:被相続人の子
- 第2順位:被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)※
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹
- ※被相続人の直系尊属の間では、被相続人と親等の近い者が先順位となります(民法第889条第1項第1号)。
最上位の法定相続人全員(配偶者を除く)が相続放棄をした場合、次の順位者へ相続権が移動します。
(例)被相続人の子全員が相続放棄をした場合
→被相続人の直系尊属へ、被相続人と親等が近い順に相続権が移ります。直系尊属がいない場合や、直系尊属全員が相続放棄をした場合には、被相続人の兄弟姉妹へ相続権が移ります。
なお、配偶者が相続放棄をした場合には、その相続分は上記の相続順位に従った最上位者に移ります。
(例)被相続人の配偶者と子2人が相続人のケースで、配偶者が相続放棄をした場合
→配偶者の相続分が子2人に移り、子2人が半分ずつの相続権を取得します。 -
(2)相続放棄をしても、代襲相続は発生しない
被相続人が死亡する前に被相続人の子または兄弟姉妹が死亡した場合は、死亡した者の子が相続権を取得します(民法第887条第2項、第889条第2項)。
これを「代襲相続」といいます。
また、被相続人の孫以降の子が死亡した場合には、さらにその子による「再代襲相続」も認められています(民法第887条第3項)。
相続欠格(民法第891条)または相続廃除(民法第892条)によって相続権を失った場合にも、代襲相続が発生します。
他方で、相続人が相続放棄をした場合には、代襲相続は発生しません。
たとえば被相続人の子が相続放棄をしても、さらにその子(=被相続人の孫)が相続権を取得することはないという点に注意してください。
3、相続人全員が相続放棄をするとどうなる? 注意点は?
相続放棄は各相続人が単独で行うことができる手続であるため、すべての相続人が共同で行う必要はありません。
しかし、被相続人が多額の借金を負っていた場合などには、相続人全員が相続放棄をすることもあります。
相続人全員による相続放棄も可能ですが、その際には、相続財産の帰属に関するルールや実務上の手続に関して注意すべき点があります。
-
(1)全員が相続放棄をした場合における相続財産の帰属
相続人が全員相続放棄をした場合、相続人がいなくなります。
この場合、相続財産は最終的に国庫に帰属することになりますが、それまでには以下の手続きを経る必要があります。① 相続財産清算人の選任・相続人の捜索等の公告
利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産清算人(※)を選任します(民法第952条第1項)。
(※2023年4月1日施行の改正民法により、相続財産管理人から制度変更)
この場合、家庭裁判所は遅滞なく、相続財産清算人を選任した旨、および相続人があるならば一定期間内に権利を主張すべき旨を公告しなければなりません。
公告期間は6か月以上に設定されます(同条第2項)。
② 相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告
相続人の捜索等の公告がなされた場合、相続財産清算人はすべての相続債権者・受遺者に対し、一定の期間を定めて請求の申出をすべき旨を公告しなければなりません(民法第957条第1項)。
請求申出の期間は、2か月以上かつ相続人の捜索等の公告期間内に満了する期間に設定されます。
請求の申出をした相続債権者・受遺者に対しては、相続財産清算人が相続財産のなかから弁済を行います。
③ 特別縁故者に対する相続財産の分与
家庭裁判所は、相続人の捜索等の公告期間内において、相続人としての権利を主張する者がない場合において相当と認めた場合には、被相続人と特別の縁故があった者(=特別縁故者)に対して、相続財産の全部または一部を与えることができます(民法第958条の2第1項)。
特別縁故者による相続財産の分与請求は、相続人の捜索等の公告期間満了後3か月以内にしなければなりません(同条第2項)。
④ 残余財産の国庫への帰属
上記の各手続きを経て処分されずに残った相続財産は、国庫に帰属します(民法第959条)。 -
(2)全員が相続放棄をする場合の注意点
相続人全員が相続放棄をする場合には、以下の各点に注意が必要です。
① 相続財産清算人の選任申し立てが必要
相続財産を国庫に帰属させる手続きを行わせるため、相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。
申し立てには数千円程度の費用がかかるほか、相続財産が少なく相続財産清算人の報酬が支払えない場合には、申立人が報酬相当額の納付を求められます。
② 現に占有している相続財産の保存義務が残る
相続財産清算人に引き継ぐまでは、相続放棄をした時点で現に占有している相続財産の保存義務(管理義務)が残ります(民法第940条第1項)。
③ 固有の保証債務は免除されない
相続放棄をした者が被相続人の債務を保証していた場合、相続放棄をしても、当該保証債務は免除されません。
保証債務は相続放棄をした者固有の債務であり、相続債務ではないためです。
4、相続放棄を検討する場合は弁護士に相談を
相続放棄には原則として3か月以内の期限があるほか、法定単純承認(民法第921条)にも注意しなければなりません。
さらに、相続人全員が相続放棄をする場合には、相続財産清算人の選任申し立てなどの対応も必要になります。
相続放棄を行う際には、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、相続放棄の手続きを問題なく完了できるように、財産調査や申述書の作成に戸籍資料の取得などをサポートいたします。
相続財産清算人の選任申し立てについても、一括して弁護士に依頼することが可能です。
5、まとめ
相続放棄をするかどうかは、メリットとデメリットの双方をふまえて、適切に判断する必要があります。
とくに相続人全員が相続放棄をする場合には、その後の手続きなどについて弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所では、遺産相続に関するご相談を受け付けております。
グループ内に税理士も所属しているため、相続税の申告などについてもまとめて相談していただくことができます。
遺産相続についてお悩みの方や、相続放棄を検討されている方は、まずはベリーベスト法律事務所にご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています