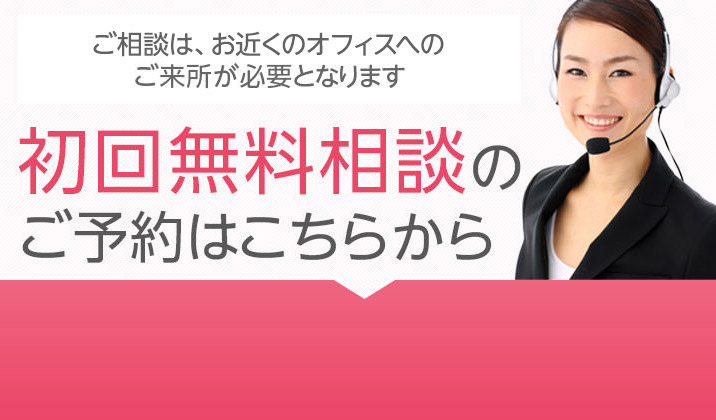住宅ローンの連帯債務は離婚するとどうなる? 外れるための対処法も解説
- 離婚
- 離婚
- 連帯債務

沼津市統計書によると、令和4年の静岡県沼津市の離婚件数は465件でした。
離婚の際、住宅ローンが完済していないケースは少なくありません。特に、夫婦が住宅ローンの連帯債務者になっている場合、離婚しても連帯債務は解消されないため注意が必要です。
離婚時に連帯債務を解消する方法としては、単独ローンへの借り換え、住宅の売却、自己破産などが挙げられます。本記事では、住宅ローンの連帯債務が離婚によってどうなるのかについて、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士が解説します。


1、住宅ローンの連帯債務とは?
夫婦で連帯債務型の住宅ローンを組んでいる場合、離婚時にはさまざまなポイントに注意しなければなりません。まずは、連帯債務型の住宅ローンとは何かについて確認しましょう。
-
(1)連帯債務とは
「連帯債務」とは、複数の者が連帯して負担する債務をいいます。連帯債務者はいずれも、債権者に対して債務全額を弁済する責任を負います。
たとえば、夫婦が金融機関から連帯債務型の住宅ローンを借り入れているとします。
この場合、金融機関は、弁済期が到来した住宅ローンの返済を、夫婦のどちらに対しても請求可能です。
仮に夫と妻の間で、住宅ローンの負担を半分ずつと合意していても、金融機関にはそのような合意は関係ありません。夫婦は連帯債務者なので、金融機関から請求を受けたら、弁済期が到来した住宅ローン債務の全額を返済しなければなりません。 -
(2)共同で組む住宅ローンのパターン|連帯債務型・連帯保証型・ペアローン
夫婦が共同で組む住宅ローンには、以下の3つのパターンがあります。
① 連帯債務型
夫婦が連帯債務者として、1本の住宅ローンを共同で借り入れます。
金融機関は夫婦の両方に対して、弁済期が到来した住宅ローンの返済を請求できます。
② 連帯保証型
夫婦のうちいずれか一方が住宅ローンを借り入れ、もう一方が連帯保証人になります。
金融機関は、基本的には主たる債務者に対して、弁済期が到来した住宅ローンの返済を請求します。しかし、主たる債務者が返済を遅滞した場合は、連帯保証人に対して請求が行われます。
③ ペアローン
夫婦がそれぞれ住宅ローンを借り入れた上で、互いに相手方の住宅ローンの連帯保証人になります。連帯債務型や連帯保証型とは異なり、住宅ローンは2本となります。
連帯債務型・連帯保証型・ペアローンは、それぞれ返済に関するルールなどに違いがあります。離婚に当たって住宅ローンの処理を検討する際には、金融機関と締結した住宅ローン契約の内容を確認しましょう。
2、離婚する際の住宅ローンに関する注意点
連帯債務型の住宅ローンを組んでいる夫婦が離婚する場合は、以下のポイントに注意しながら離婚協議を行いましょう。
-
(1)離婚しても連帯債務はなくならない|元配偶者の延滞分は請求される
夫婦が離婚しても、住宅ローンの連帯債務が自動的に解消されるわけではありません。離婚は連帯債務者である夫婦の内部事情に過ぎず、債権者である金融機関には関係がないためです。
たとえば夫婦が離婚する際に、男性側が連帯債務型の住宅ローンを払い続けて、女性側が子どもと家に住み続けるといったケースはよく見られます。
しかしこのようなケースにおいて、もし男性側が住宅ローンの支払いを遅滞すると、連帯債務者である女性側に対して返済の請求が行われる点に注意が必要です。
住宅ローンを支払えなければ、家は競売にかけられてしまいます。さらにオーバーローン(=住宅ローンの残高が家の価値を上回っている状態)の場合は、自己破産に追い込まれてしまうおそれもあるので十分ご注意ください。
離婚後も連帯債務が残ることについて懸念がある場合には、後述する方法によって連帯債務を解消しましょう。 -
(2)住宅ローンも財産分与の際に考慮する必要がある
夫婦が離婚する際には、共有財産を公平に分ける「財産分与」を行います(民法第768条、第771条)。
夫婦が婚姻中に取得した財産は、原則として財産分与の対象です。住宅ローンを組んで自宅を購入したのが婚姻中であれば、自宅も財産分与の対象になります。その場合は、マイナスの財産ともいえる住宅ローンの金額も考慮するのが公平です。
ただし、夫婦間で合意したとしても、住宅ローンの債務者を勝手に変更することはできません。債務者変更には、債権者である金融機関の同意を得る必要があります。後述するように、金融機関の審査を経て単独ローンに借り換える方法などが考えられますが、簡単に認められるわけではない点に注意が必要です。
また、住宅ローン残高を控除した後の住宅の価値が高額である場合や、逆に大幅なマイナスである場合には、金銭などによって財産分与の割合を調整する必要が生じます。
しかし、夫婦がいずれも十分な金銭を有していないときは、財産分与のバランスが取れなくなってしまいます。
このようなケースでは、財産分与の後払いや、他の離婚条件との兼ね合いなどを検討して調整することが考えられます。どのような調整方法が適切であるかは状況によって異なりますので、弁護士にご相談ください。
お問い合わせください。
3、離婚時に住宅ローンの連帯債務を解消する方法
連帯債務型の住宅ローンを組んでいる夫婦が離婚する際、離婚後も連帯債務を維持して返済を続けるのは、かなりリスクが高いのでお勧めできません。
離婚に伴って住宅ローンの連帯債務を解消する方法としては、以下の例が挙げられます。
-
(1)単独ローンに借り換える
離婚後も自宅を維持し、どちらかが自宅に住み続ける場合は、連帯債務型の住宅ローンを単独ローンに借り換えることで、連帯債務関係は解消されます。
ただし、単独ローンへの借り換えに当たっては、金融機関の審査を通過しなければなりません。単独ローンの場合は、単独債務者となる人の収入や属性だけが審査の対象となるため、連帯債務型よりも審査が厳しくなる点に注意が必要です。
単独ローンへの変更が認められる例としては、一方配偶者の両親が健在で、長期間十分な収入が期待できる場合に、両親を新たな連帯債務者・連帯保証人とするという方法が挙げられます。
他に高価な財産があれば、これに担保を付するという条件で、単独ローンへの変更が認められる場合もあります。
なお住宅ローンについては、原則として債務者(名義人)がその住宅に住んでいなければならないというルールがあります。
連帯債務型の住宅ローンを借り続けながら、夫婦が離婚してどちらか一方しか住んでいない状態になると、期限の利益を喪失して一括返済を求められてしまうおそれがあるので十分ご注意ください。 -
(2)住宅を売却する
住宅を売却することは、連帯債務型の住宅ローンを解消するための分かりやすい方法のひとつです。
住宅を売却するに当たっては、住宅ローンを完済して抵当権を抹消しなければなりません。オーバーローンの場合は、売却代金だけでは住宅ローンを完済できないので、返済用資金を別途準備する必要があります。
住宅ローンを完済できない場合は、住宅の売却は困難なので、別の方法を検討しなければなりません。 -
(3)返せない場合は自己破産をする
オーバーローンで住宅の売却が難しく、住宅ローンを完済できない場合は、自己破産をすることも選択肢となります。
自己破産は、財産を処分して債権者に配当した後、原則として残った債務全額を免除する手続きです。連帯債務型のペアローンが支払不能となった場合は、夫婦がそれぞれ自己破産を申し立てることになります。
自己破産をすると、自宅が処分されることは避けられません。また、自宅以外の高価な財産や、解約返戻金のある保険なども処分されてしまいます。
また、個人信用情報機関に異動情報が登録され、一定期間はローンやクレジットカードを利用できなくなる点も、自己破産のデメリットと言えます。
その一方で、99万円以下の現金や生活に必要な財産は処分されず、破産手続開始決定以降に取得した財産も処分の対象外です。したがって、自己破産をしても最低限の生活レベルは保障されることになります。
また、住宅ローンを含めて、返済困難な債務が全額免除される点は、自己破産の大きなメリットです。
自己破産にはメリット・デメリットの両面があり、向いている人とそうでない人がいるので、弁護士のアドバイスを踏まえて判断しましょう。
4、住宅ローンの連帯債務者が離婚する際、弁護士に相談すべき理由
連帯債務型の住宅ローンを組んでいる夫婦が離婚する際には、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することには、主に以下のメリットがあります。
- 連帯債務を解消するための具体的な方法についてアドバイスを受けられる
- 住宅ローンを考慮した上で、適切な財産分与の方法についてアドバイスを受けられる
- 財産分与以外の離婚条件についても、代理人として交渉を任せられる
- 離婚協議が決裂した場合は、調停や訴訟についてもサポートを受けられる
離婚にまつわる悩みは多岐にわたります。離婚問題の解決実績が豊富な弁護士に相談し、併せて住宅ローンの問題解決を目指しましょう。
5、まとめ
連帯債務型の住宅ローンを借りている夫婦が離婚する際には、その処理についてさまざまな部分で注意を要します。弁護士のアドバイスを受けながら、適切な住宅ローンの処理方法を検討しましょう。
ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスは、離婚に関するご相談を随時受け付けております。連帯債務型の住宅ローンの処理方法についても、ご状況に応じてアドバイスいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています