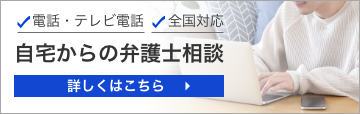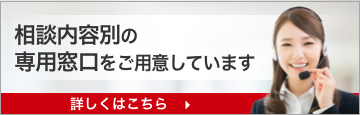著作権譲渡契約の際に知っておくべきポイントを解説
- 商標・特許・知的財産
- 著作権
- 譲渡

令和元年11月、日本音楽著作権協会(JASRAC)が著作権を管理する音楽著作物を無断利用したとして、静岡県袋井市所在の演奏会事業者らが著作権法違反の疑いで逮捕される事件がありました。本事件は、著作権者から著作権の譲渡や利用許諾を得ていないのにもかかわらず、当該著作物を使用・収益したことが罪に問われたものです。
著作権は会社にとって重要な資産のひとつです。その活用を著作権者が他の個人や法人に認める場合にも、正当な対価を受ける権利があります。ただし、適切に対価を受けるためには、著作権譲渡契約を締結したうえで譲渡や利用許諾の条件を取り決めることが重要になります。
本コラムでは、著作権という知的財産権のあらましから著作権譲渡契約を締結するときのポイントについて、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士が解説します。
1、著作権とは?
-
(1)知的財産権とは?
著作権は、知的財産権のひとつです。
会社は自社が所有する著作権などの知的財産権を利用して、事業を有利に展開することが期待できます。
また、第三者に対して自社の知的財産権の使用を許可することによってライセンス収入を得ることができるうえに、それを譲渡して対価を得ることもできるのです。
また、IT企業のように担保価値のある不動産を保有していない会社にとって、知的財産権は「質権や譲渡担保などを設定して融資を受ける」「証券化スキームを利用する」などの、資金調達手段として活用できるという点でも、重要な資産なのです。 -
(2)著作権とは?
著作権とは、著作物を創作した場合に当該著作物について発生する権利のことです。
実用新案権や特許権などの他の知的財産権と異なり、行政庁への登録を経ることなく著作物を創作したときに、当然に発生する権利であることが特徴になります。
また、著作権とは、著作物に関する権利の総称です。
したがって、「著作権」というひとつの権利が存在するわけではありません。
たとえば、著作物をコピーする権利を「複製権」、音楽を演奏する権利を「演奏権」、著作物を譲渡する権利を「譲渡権」というように、さまざまな権利が著作権に含まれるのです。
著作権法第2条第1項によりますと、著作権は「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
しかし、このうち「文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」とはあまり厳密に解釈されているわけではありません。
一般的には、出版された小説や漫画、音楽、映画などが著作物に該当することについては、よく知られています。そのほかにも。演劇、地図、コンピュータープログラム、技術書など、著作物の範囲は多岐にわたるのです。
そして、そのなかには必ずしも「文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」に含まれるとは言い切れないものもあります。
このように、創作と同時に権利を取得できるうえに、その対象である著作物の範囲も多岐にわたり企業の収益源にもなることから、著作権は企業にとって極めて重要な財産です。特に近年は、ソフトウエアのデータベースなども重要な著作物として考えられるようになっていますので、その業種に携わる会社にとっては、著作権は今後ますます重要になる権利でしょう。 -
(3)譲渡できない著作権とは?
著作権は、著作者(著作物を創作した人)に発生する権利です。
そして、著作権は、他の知的財産権と同様に譲渡したり、使用を許諾したりすることができます。さらに、無断で第三者が著作物をコピーしたり勝手に使用したりした場合には、著作権侵害として損害賠償請求や差し止め請求などを行うこともできるのです。
ただし、数ある著作権のうち、著作権法第59条の規定により著作者の人格的利益を保護する「著作者人格権」は著作者の一身に専属する権利であるため、譲渡することができません。
著作者人格権は、具体的には以下の3つの権利となります。- 公表権……著作権者の著作物を公表するか否か、決定する権利
- 氏名表示権……著作権者の著作物に著作者名を表示するか、あるいはどのような著作者名にするか、著作者が決める権利
- 同一性保持権……著作者の著作物の内容などを、著作者の意に反して使用者の都合で改変されない権利
-
(4)新規ビジネスと著作権
知的財産の分野では、ソフトウエアなどにかぎらず新たなビジネススキームが次々と生み出されています。その生み出されるスピードに、法令等によるルール作りが必ずしも追いついていないというのが現状です。
そのため、新規ビジネスの著作権については、それをめぐる紛争の末に、裁判所の判断が確定してからはじめて適法・違法が一般化するというケースが多いのです。
たとえば、近年は個人が自ら所有する書籍をスキャナー等で読み取り電子書籍化する「自炊」行為を第三者が代行する「自炊代行」が著作権侵害に該当するか否かについて訴訟がありました。
これに対して東京地方裁判所は、「自炊代行は著作権侵害に該当する」という旨の判決を言い渡したのです。
この判決のポイントは、個人が所有する著作物を複製するかぎりは私的複製として著作権侵害に該当しないものの、第三者である業者が事業として代行することは著作権侵害に該当するということです。
2、著作権の「譲渡」と「利用許諾」の違い
著作権の「譲渡」と「利用許諾」の違いを簡単に表現すると、著作権の「売却」と「レンタル」の違いということになります。
-
(1)著作権の譲渡
著作権を譲渡することとは、著作権者としての地位が移転することを意味します。
たとえばA社が保有する著作権をB社に譲渡すると、A社は著作権者ではなくなりB社が著作権者になります。
したがって、B社は著作権者として当該著作権から得られる利益を独占的に享受することができるほか、もし他社から著作権の侵害があった場合は紛争の当事者として争うことになるのです。 -
(2)著作権の利用許諾
譲渡とは異なり、著作権の利用許諾では、著作権者としての地位は移転しません。
先ほどのA社とB社の例えでいいますと、B社は利用許諾を受けた著作権から生じる利益を享受することができますが、あくまで利用許諾はレンタルにすぎないために、著作権者は引き続きA社です。
したがって、他社から著作権の侵害があった場合に紛争の当事者として争う主体は、A社ということになるのです。
なお、著作権の利用許諾は契約の内容によって「独占的利用許諾」と「非独占的利用許諾」に分かれます。
独占的利用許諾の場合、B社は譲渡を受けた場合と同様に独占的に当該著作権を活用する権利が生じます。
一方で、非独占的利用許諾であればB社は当該著作権を独占的に活用することはできません。
著作権者であるA社も引き続き活用するかもしれませんし、A社はC社やD社など他の会社にも同時に非独占的利用許諾の契約を締結することができるのです。
3、著作権を譲渡する場合は「著作権譲渡契約書」を交わす
著作権の譲渡契約にかぎらず、民法上、契約は当事者間の口頭によるものでも原則として有効に成立します。
しかし、後日のトラブルを避けるため、契約書(著作権譲渡契約書)を締結しておくことが一般的です。
-
(1)すべてを譲渡する場合
著作権のすべてを譲渡する場合、契約書にその旨だけを記載しておくだけでは不十分です。著作権法第61条第2項では、「著作権を譲渡する契約において、第27条または第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する」と規定されています。
ここでいう第27条は著作物の翻訳権および翻案権、第28条は二次的著作物を利用することに関する原著作者の権利のことです。
著作権法第61条第2項の規定により、著作権譲渡契約書にこの第27条および第28条の譲渡に関することを明記しておかないと、第27条および第28条の権利は譲渡されないことになります。
したがって、著作権譲渡契約書には「すべての著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)を譲渡する」というようにしておくことをおすすめします。
また、著作権のすべてを譲渡するといっても、先述のとおり著作者人格権は譲渡することができません。
これについても、「譲受人は著作者人格権について一切行使しないものとする」などと、条項に設けておいてください。 -
(2)一部を譲渡する場合
著作権の一部を分割して譲渡する場合は、著作権譲渡契約書に分割する著作権(支分権)の範囲、譲渡する期間を指定するのであればその期間、活用できる地域を限定するのであればその地域を、明確に規定しておく必要があります。
あいまいな規定では、後日のトラブルを招きかねません。
4、著作権譲渡契約書のひな形をそのまま利用するのは注意が必要
インターネットでは、著作権譲渡契約書の「ひな型」が公開されているサイトもあります。
しかし、ひな形はあくまでひな形です。
ひな型は契約当事者が最低限契約書の内容に盛り込むべきことを示すために作成されており、あいまいな表現も多く、契約当事者がトラブルに巻き込まれた場合を十分に想定して作成されているものではありません。
したがって、ひな型をそのまま丸写ししただけの契約書で著作権を譲渡する契約を締結することは、得策ではないのです。
特に著作権譲渡契約は、事例ごとの個別性が強くなります。
著作権譲渡契約書は譲渡する著作権や譲渡内容を十分にふまえながら、後日のトラブルを避けるため、慎重に作成する必要があるのです。
5、まとめ
著作権の譲渡あるいは譲り受けをご検討のときは、ぜひ、弁護士にまでご相談ください。
知的財産に関する経験と知見のある弁護士や事務所であれば、法的なアドバイスはもちろんのこと、後日にトラブルが起きないような著作権譲渡契約書の作成を依頼することができます。
沼津市や近隣市町村にお住まいで、著作権譲渡に関するお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所までご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています