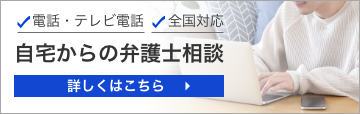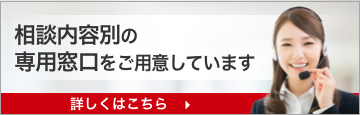自社の特許権を侵害されたときにとるべき対応を解説
- 商標・特許・知的財産
- 特許権
- 侵害

特許庁の公表資料によると、2020年中の静岡県における特許登録件数は1960件でした。特許登録件数の全国最多は東京都(7万2187件)であり、大阪府、愛知県、神奈川県、京都府、兵庫県と続いて、静岡県は全国で第7位となっています。
他社の製品等が自社の特許権を侵害している場合、売り上げが分散して収益が減少するおそれがあります。もし自社の特許権が侵害されていることを発見した場合には、早急に対応する必要があります。
特許権侵害の被害を回復するためには、法律上のさまざまな手段を講じることができます。特許発明の不正実施を許さず、自社の正当な権利を守るため、お早めに弁護士や弁理士へご相談ください。本コラムでは、特許権侵害の要件や、特許権侵害を受けた場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士が解説します。
1、特許権の侵害とは?
まずは、どのような行為が特許権の侵害に該当するのかについて、特許法上の要件を解説します。
-
(1)特許権の技術的範囲に属する発明を、無断で業として実施すること
特許権者は、「業として特許発明の実施をする権利」を専有します(特許法第68条本文)。
したがって、特許権の侵害とは、特許発明を特許権者に無断で業として実施することを意味します。
「実施」とは、以下のいずれかに該当する行為です(特許法第2条第3項)。① 物の発明の場合
生産、使用、譲渡等、輸出、輸入、譲渡等の申し出
② 方法の発明の場合
使用
③ 物を生産する方法の発明の場合
その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出、輸入、譲渡等の申し出
「業として」は、個人的・家庭的な実施を除く趣旨と解されています。
つまり、単発であっても事業の一環として実施行為がなされた場合には、「業として実施」したことになるのです。
特許発明は、「特許権の技術的範囲」に限り、特許権によって保護されます。
そのため、実施の対象が特許権の技術的範囲に属する発明であることが、特許権侵害の要件となるのです。
特許権の技術的範囲は、特許出願の願書に添付した特許請求の範囲(請求項)の記載に基づいて定められています(特許法第70条第1項)。
なお、特許請求の範囲の記載内容を解釈するにあたっては、明細書の記載及び図面を考慮すべきものとされています(同条第2項)。 -
(2)3種類の特許権侵害|文言侵害・均等侵害・間接侵害
特許権の侵害は、「文言侵害」「均等侵害」「間接侵害」の3種類に大別されます。
① 文言侵害
特許権の技術的範囲の構成要件をすべて満たしている場合に、文言侵害が成立します。
② 均等侵害
特許権の技術的範囲について、構成要件の一部が満たされてない場合でも、以下の要件をすべて満たす場合には均等侵害が成立します(最高裁平成10年2月24日判決)。
- 相違点が本質的部分でないこと
- 相違点を置換しても特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏すること
- 相違点の置換が容易であること
- 公知技術との同一性がなく、または容易に推考できるものでないこと
- 対象製品等が、特許請求の範囲から意識的に除外されたものであるなどの特段の事情がないこと
③ 間接侵害
上記のほか、以下のいずれかに該当する行為については間接侵害が成立します(特許法第101条)。
- 特許発明の専用品に係る生産・譲渡等・輸入・譲渡等の申し出(同条第1号、第4号)
- 特許発明による課題解決に不可欠なものに係る、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながらする生産・譲渡等・輸入・譲渡等の申し出(同条第2号、第5号)
- 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為(同条第3号)
- 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為(同条第6号)
2、特許権を侵害された場合にできること
第三者によって特許権を侵害された場合、法的には民事上の差止請求および損害賠償請求、さらに捜査機関に対する刑事告訴が可能です。
-
(1)差止請求
特許権者は、自己の特許権を侵害する者または侵害するおそれがあるものに対し、侵害の停止または予防を請求できます(特許法第100条第1項)。
これを「差止請求」と言います。
特許権侵害が継続すると、侵害製品に自社製品のシェアを奪われてしまい、自社の損害が拡大してしまうおそれがあります。
そのため、特許権侵害の事実を認識したら、速やかに差止請求を行って、侵害状態を解消することが急務となるのです。 -
(2)損害賠償請求
特許権侵害は不法行為(民法第709条)に該当し、特許権者は侵害者に対して損害賠償を請求できます。
賠償の対象となる損害の例としては、売り上げ減少等による逸失利益、損害賠償請求等にかかったコスト、企業イメージの毀損による損害などがあります。
なお、特許権侵害に基づく損害賠償請求については、特許法第102条に損害額の推定規定が設けられており、通常の不法行為よりも被害者側の立証責任が緩和されています。 -
(3)刑事告訴
特許権侵害は、特許法によって犯罪とされています。
文言侵害については「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」(特許法第196条)、間接侵害については「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」(特許法第196条の2)がそれぞれ侵害者に対して科される、または併科されます。
特許権者は、特許権侵害の事実を捜査機関(警察・検察)に申告し、犯人の処罰を求める「告訴」を行うことができます(刑事訴訟法第230条)。
告訴を受けた捜査機関は、特許権侵害の有無に関する捜査に着手して、最終的に検察官が被疑者を起訴するかどうかを判断します。
3、特許権侵害の被害を回復するまでの流れ
第三者の特許権侵害によって損害を被った場合、基本的には、以下の流れで損害賠償請求を行って損害の回復を図ることになります。
-
(1)侵害者に対して警告書を送付する
まずは侵害者に対して、「特許権侵害に当たる行為を直ちにやめるべき」という旨と、損害賠償を請求する旨の警告書を送付します。
侵害者に対して「こちらが本気で損害賠償を請求する気である」という強いメッセージを伝えるため、警告書は内容証明郵便で送付するのがよいでしょう。
また、内容証明郵便によって損害賠償を請求した場合、損害賠償請求権の消滅時効の完成を6カ月間猶予する効果も生じます(民法第150条第1項)。 -
(2)侵害者と示談交渉を行う
警告書の送付後、侵害者が侵害の事実を認めた場合には、示談交渉を開始します。
示談交渉では、発生した損害の根拠を示しつつ、損害賠償の支払いに関する条件を提示します。
金額提示に対しては、侵害者から減額の交渉を受ける可能性もあります。
その際は、訴訟等に発展した際の見通しや、早期解決のメリットなどを総合的に考慮して、自社として妥協可能なラインを設定したうえで示談交渉に臨んでください。 -
(3)示談不成立ならADR・調停・訴訟
侵害者が侵害の事実を認めない場合や、損害賠償の金額について折り合わなかった場合には、以下のいずれかの手続きによって解決を図ることになります。
① ADR(裁判外紛争処理手続)
裁判所以外の第三者機関が仲介者または判断権者となって、民事紛争の解決を図る手続きです。
当事者間の合意による和解を目指す「調停」や、第三者機関が結論を提示する「仲裁」などがあります。
特許権侵害に関するADRを取り扱う第三者機関としては、日本知的財産仲裁センターなどが例に挙げられます。
② 民事調停
調停委員が仲介者となって、民事紛争に関する当事者間の調整を行い、最終的に和解を目指す手続きです。
民事調停は簡易裁判所で行われます。
③ 訴訟
裁判所の公開法廷で当事者双方が主張・立証を行い、裁判所が判決によって紛争解決の結論を提示する手続きです。
上記の手続きを通じて損害賠償義務が確定した場合、決まった期日や金額等にしたがい、侵害者は特許権者に対して損害賠償金を支払う必要があります。
-
(4)侵害者が賠償金を支払わない場合は強制執行
侵害者が確定した損害賠償義務を履行しない場合、強制執行によって侵害者の財産を差し押さえ、特許権侵害による損害額の回収を図ります。
強制執行の申し立てには、民事執行法第22条第1項各号所定の「債務名義」が必要です。<債務名義に当たるものの例>
- 訴訟の確定判決
- 訴訟上の和解調書
- 民事調停の調停調書
- ADRの確定仲裁判断(裁判所の執行決定が必要)
- 強制執行認諾文言付きの和解公正証書
<債務名義に当たらないものの例>
- 強制執行認諾文言のない和解公正証書
- ADRの調停に基づく和解契約書(公正証書でないもの)
- 当事者が自分で作成した和解契約書、示談書など
債務名義がない場合、強制執行の申し立てを行うには、先に特許権侵害訴訟などを通じて債務名義を取得する必要があります。
4、特許権侵害を受けたら弁護士・弁理士にご相談を
特許権侵害を受けた場合、侵害の事実や損害額についての主張を行うためには、特許権侵害の要件をふまえた説得的な主張構成を組み立てることが大切です。
特許権侵害の有無および金額に関する検討は、極めて専門性が高い分野のため、専門家である弁護士・弁理士に依頼することをおすすめいたします。
ベリーベスト法律事務所には、弁護士とともに弁理士が在籍しており、緊密に連携を取りながら、お客さまの損害が一日も早く回復されるためにサポートいたします。
特許権侵害の事実を発見した場合には、お早めに、弁護士・弁理士へご相談ください。
5、まとめ
特許権侵害を受けた場合、差止請求によって損害の拡大を防止し、さらに損害賠償請求を通じて損害の回復を図ることができます。
また、侵害者に対する刑事処分を求めたい場合には、捜査機関に対する刑事告訴も検討しましょう。
特許権侵害による損害を最小限に食い止めるには、差止請求・損害賠償請求等へ早期に着手することが非常に大切です。
ベリーベスト法律事務所では、弁護士・弁理士がグループ内で緊密に連携をとりながら、侵害行為の差し止めおよび適正な条件での賠償金獲得を一日も早く実現できるように、尽力いたします。
他社による特許権侵害への対応にお困りの方は、ぜひ一度、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています